セリエAに新たな風を吹き込む若き指揮官、ファビオ・ピザカーネ監督。カリアリのユースチームを率いて見事な成功を収め、トップチームの監督へと就任した彼の戦術は、一部のサッカーファンから熱い視線を集めています。
「彼のサッカーは一体何が特徴なんだろう?」「フォーメーションや選手の動きはどうなっているの?」
この記事では、そんなピザカーネ監督が描くサッカーの全体像から、攻撃と守備の具体的な特徴まで、一つひとつわかりやすく解説していきます。
ファビオ・ピザカーネ監督の基本思想とフォーメーション
まずは、ピザカーネ監督の戦術の根幹となる「考え方」から見ていきましょう。
基本フォーメーションと戦術哲学
ピザカーネ監督のサッカーを語る上で一番の特徴は、「フォーメーションはあくまで数字に過ぎない」という考え方です。試合前は「4-3-1-2」「4-3-2-1」や、強豪相手の場合「3-5-2」といった形で紹介されますが、試合が始まれば選手たちはまるで生き物のようにポジションを変えていきます。
彼の戦術哲学の核にあるのは、「原則」をチーム全体で共有すること。例えば、「ボールを奪ったら素早く縦へ」「守るときは選手間の距離をコンパクトに」といった約束事です。選手たちはその約束事を守りさえすれば、状況に応じて最も効果的なプレーを選ぶことが許されています。これにより、相手チームにとっては予測が難しい、柔軟なサッカースタイルが生まれるのです。
選手の個性を活かす柔軟なアプローチ
原則を重視するスタイルは、選手の個性を最大限に引き出すことにも繋がります。
例えば、ドリブルが得意な選手には「どんどん仕掛けていい」と背中を押し、パスでチャンスを作るのがうまい選手には、自由に動いて攻撃の起点になる役割を与えます。
監督が全ての動きを細かく指示するのではなく、大枠のルールの中で選手たちが自ら考えてプレーする。このアプローチによって、選手たちは責任感と自信を持ってピッチに立つことができ、チーム全体のパフォーマンス向上に繋がっているのかもしれませんね。
ユース時代から続く一貫したコンセプト
この戦術スタイルは、トップチームの監督になってから始まったものではありません。彼が率いたカリアリのプリマヴェーラ(ユースチーム)は、同じコンセプトのサッカーを展開し、クラブ史上初となるコッパ・イタリア優勝という快挙を成し遂げました。
この成功体験が、彼の戦術がカテゴリーを問わず通用するものであることの何よりの証明です。ユース時代から育んできた一貫した哲学こそが、ピザカーネ監督の最大の武器と言えるでしょう。
ピザカーネ戦術の【攻撃】の特徴
ピザカーネ流のカリアリはどのようにしてゴールを奪うのか、攻撃の具体的な特徴を3つのポイントで見ていきます。
GKを起点としたビルドアップ
現代サッカーにおいて、ゴールキーパーはただゴールを守るだけの選手ではありません。ピザカーネ監督のチームでも、GKは「最初の攻撃者」としての重要な役割を担います。
守備陣が相手のプレッシャーを受けると、GKへ一度ボールを預けます。GKが落ち着いてボールを持つことで、相手フォワードを引きつけ、疑似カウンター気味にその背後に生まれたスペースへパスを供給する。こうして効果的な攻撃の第一歩を踏み出します。
ボール奪取後の素早い切り替え(トランジション)
ピザカーネ戦術の真骨頂とも言えるのが、守備から攻撃へと切り替わる「トランジション」の速さです。
ボールを奪った瞬間、まるでスイッチが入ったかのように5〜6人もの選手が前線へ駆け出していきます。相手の守備陣形が整う前に、一気にゴール前まで迫るこの「垂直的」な攻撃は、非常にスリリングで見応えがあります。このスピーディーな展開こそが、カリアリファンを魅了する理由の一つです。
MFの積極的な前線への飛び出し
彼の攻撃をより予測不可能なものにしているのが、ミッドフィルダーの動きです。
ピザカーネ監督のカリアリでは、MFが積極的に相手のディフェンスラインの裏へ飛び出していきます(特に「秘密兵器」アドポがゴール前に走り込む動きが「戦術的な仕掛け」として注目されています)。フォワードの選手だけでなく、MFもゴール前に顔を出すことで、相手ディフェンダーは誰をマークすれば良いのか混乱してしまいます。この動きが、ゴールチャンスを数多く生み出す秘訣となっているのです。
ピザカーネ戦術の【守備】の特徴
次に、魅力的な攻撃を支える守備の仕組みについて解説します。
コンパクトな守備ブロックの形成
ピザカーネ監督が守備において最も重視するのが「コンパクトさ」です。フォワードからディフェンダーまでの距離を短く保ち、チーム全体が一つの塊(ブロック)となって動きます。
選手間の距離が近いため、相手はパスを通すスペースを見つけるのが非常に難しくなります。たとえ一人が抜かれても、すぐに近くの味方がカバーに入れる。この組織的な守りが、チームに安定感をもたらしていると言えるでしょう。
チーム全体で連動する組織的な守り
「守備はディフェンダーだけがするものではない」というのが、彼の考え方です。攻撃的な選手も含めた11人全員が、ボールを奪うために連動して動きます。
フォワードの選手が相手のパスコースを限定し、それに合わせて中盤の選手がボールを奪いに行く。チーム全体が網を張って相手を追い込むような連携プレーが見られます。
状況に応じたプレッシングの使い分け
常に前線からがむしゃらにボールを追いかけるわけではない、という点も彼の守備の巧みさです。
あえて相手にボールを持たせて前進させ、特定のエリアに誘い込んでから一気にプレッシャーをかけてボールを奪う。こうした「罠を仕掛ける」ような守備も行います。常に全力でプレスをかけるのではなく、試合の流れや相手に応じて賢く戦う。ピザカーネ監督はそういった冷静な判断力も持ち合わせています。
まとめ
今回は、カリアリを率いる若き智将、ファビオ・ピザカーネ監督の戦術を深掘りしました。
重要ポイントは「フォーメーションに固執せず、原則で戦う」という彼の哲学です。選手間の距離を常に短く保つ「コンパクトさ」を土台に、ボールを奪えば一気に縦へ仕掛ける「素早いトランジション」でゴールを狙います。
そのスタイルは、GKを含めた全員攻撃、そして前線の選手も含めた全員守備で成り立っており、モダンなサッカーを体現しています。
ぜひ次のカリアリの試合では、ピザカーネ監督がピッチに描く設計図を読み解くような、新しい視点で楽しんでみてください。
この記事を読んで、「この監督はこんな戦術を使うんだな」とイタリアサッカーの新たな魅力に気付いていただけたなら幸いです。
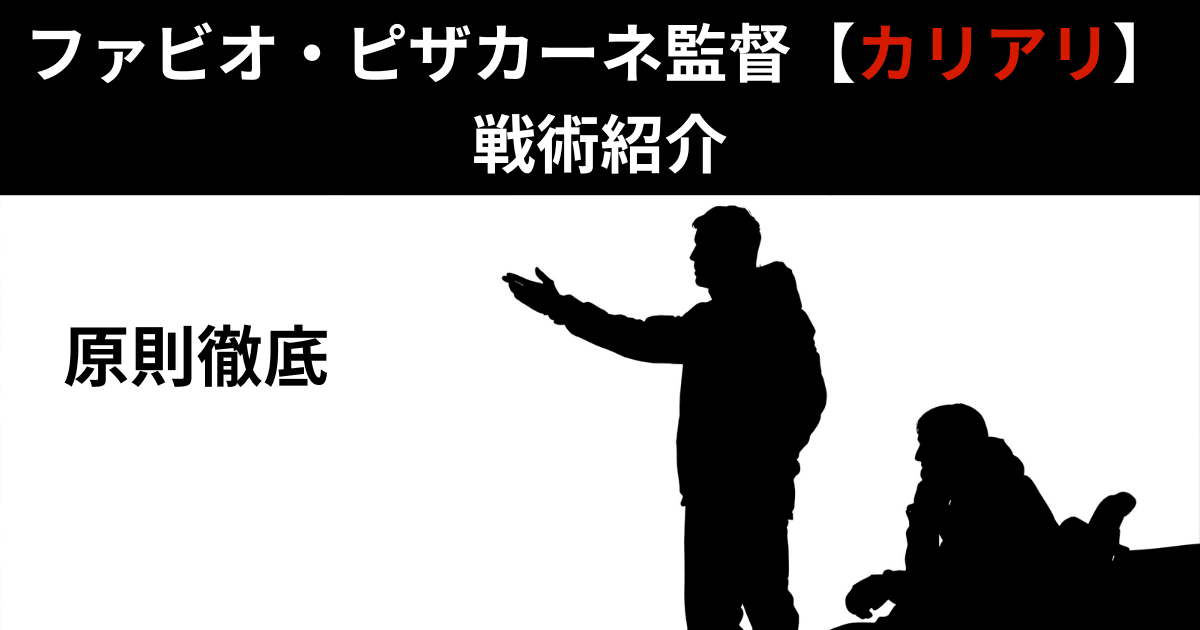
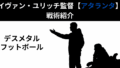
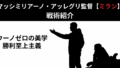
コメント